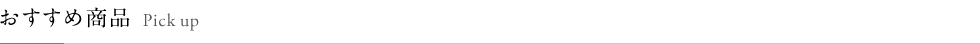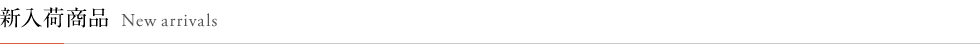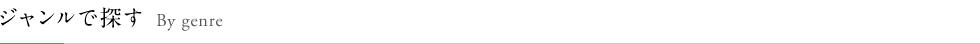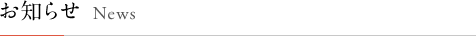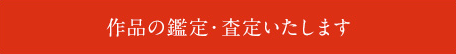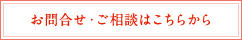-
2024.04.12
品川宿交流館 「納札交換札」展 4/16(火)~21(日)
-
2024.03.23
注意喚起 川瀬巴水初摺り木版画とみせかけたもの
-
2024.03.12
ありがとうございました。川瀬巴水 初期摺木版画展示即売会 終了
-
2024.02.22
THE 新版画展 版元渡邊庄三郎の挑戦 2024.1.26~3.18 島根県立美術館にて開催中
-
2024.02.22
川瀬巴水展 2024.1.24~3/6 高松市美術館にて開催中